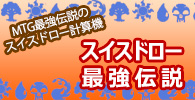カードが禁止カードになってしまう5つの理由

みなさんこんにちは。
つい先日、新たな禁止カードが制定されましたが、そもそも禁止になる理由って何?
ということで、禁止になる理由をまとめてみました。
1.あまりに強い。あまりに使い勝手が良い。
禁止カードの大抵は、この理由で禁止されることが多いです。
理由としては、それらのカードが横行しデッキの幅を狭め、ゲームをつまらなくしてしまうという懸念を抱えてしまうからです。
2.ほとんどのデッキに入ってしまう。
一つ目の理由と通ずるところもありますが、この場合は、強さはあまり関係がなく、デッキを作成する段階での問題です。
基本的に、デッキ制作にはコンセプトメイクから取捨選択の余地があるものとされますが、どんなコンセプトのデッキでも入ってしまう基本地形のようなカードが存在します。そのため、そういったカードは禁止になることがあります。
3.あまりにも早く勝利してしまうコンボ
禁止カードは、そのカード単体だけでなく、コンボによってもその強力な効果を発揮することがあります。
そのため、モダンでは3ターン、レガシーでは2ターン以内に勝利を決められてしまうデッキを基準とし、そのデッキの弱体化のためにパーツ等が禁止されることがあります。
因みに以下の6枚が初期手札になりかつ、先行だった場合、1ショットキル(1ターンキル)が実装できてしまうコンボです。
※現在は「猛火の群れ」がモダン禁止カードになっているのでできません。
4.再録禁止
Leering Gargoyle / 抜目ないガーゴイル (1)(白)(青)
クリーチャー — ガーゴイル(Gargoyle)
飛行
(T):抜目ないガーゴイルはターン終了時まで-2/+2の修整を受けるとともに飛行を失う。
2/2
これは、カードの性能はまったく関係なく、再録が禁止されているカードです。
それらのカードは、再録禁止カード一覧に収められているものがすべてです。これはメルカディアン・マスクス以降のカードは存在せず、また今後変更されることもないとされています。
目的としては、再販しないことによりカードの価値の暴落を防ぐことをアピールするものであり、上記のように強くないカード(カスレア)もこれに含まれています。
5.アンティ
Bronze Tablet / 青銅のタブレット (6)
アーティファクト
アンティを賭けてプレイしない場合、プレイを開始する前に青銅のタブレットをあなたのデッキから取り除く。
青銅のタブレットはタップ状態で戦場に出る。
(4),(T):対戦相手1人がオーナーであるトークンでないパーマネント1つを対象とし、青銅のタブレットとそれを追放する。そのプレイヤーは10点のライフを支払ってもよい。そうした場合、青銅のタブレットをオーナーの墓地に置く。そうでない場合、そのプレイヤーは青銅のタブレットのオーナーになり、あなたはもう一方の追放されたカードのオーナーになる。
現在では、死語となっていますが、当時はアンティというルールが存在していました。
内容は、カードの効果によって、ゲーム内外からカードの所有権を奪うといったものです。
日本ならびに各国の賭博禁止地域においてこのゲームをおこなうと、賭博罪に問われる恐れがあります。
そのため、アンティ関連の効果を持つカードはすべて禁止カードとなっています。
こうして見ると、禁止カードといってもさまざまな理由で禁止になっているんですね。
個人的にはアンティは衝撃的でした。何か別のゲームになってしまう気がします。
←TOPに戻る